二次試験(論文/選択科目)の対策!
特許庁のWebサイトで公開されている過去問の中から、理工IV(生物)の「生物化学」を解いてみました。
今回は、2016年度(平成28年)の問題です。
ボクなりの回答と、ボクが考えた派生問題を共有させていただきます。

おかしな箇所があれば、Comment欄にてご指摘ください。
2016年度の過去問
問1(計30点)
1.以下の事項について、空欄の( ① )から( ⑮ )に適切な語を入れよ。ただし、同じ番号には同じ語が入る。
単糖分子は、( ① )基かケトン基のいずれか一つと複数のヒドロキシ基を有する。( ① )をもつ糖をアルドース、ケトン基をもつ糖を( ② )と呼ぶ。血糖とも呼ばれるヒト生体内の代表的単糖は( ③ )である。
① アルデヒド
② ケトース
③ グルコース

アルドースの代表は「グルコース、マンノース、ガラクトース」。一方、ケト―スの代表は「フルクトース」。
リン脂質は構造中に( ④ )結合をもつ脂質の総称である。脂肪酸などを単純脂質と呼ぶのに対し、リン脂質は( ⑤ )脂質と呼ばれる。リン脂質は親水性と( ⑥ )の二つの性質を有するため、生体内では( ⑦ )層を形成して細胞膜を構成することができる。
④ エステル
⑤ 複合脂質
⑥ 疎水性
⑦ 脂質二重

細胞内における脂肪酸の最も重要な機能は「膜」をつくること。
この膜は、主にリン脂質からなります。
生体を構成する基本的なアミノ酸を標準アミノ酸とも呼ぶが、硫黄原子を含む標準アミノ酸は( ⑧ )と( ⑨ )である。このうち、( ⑨ )は翻訳反応時の開始アミノ酸としても利用されている。ヒトは( ⑨ )を食物から摂取する必要があり、このようなアミノ酸を( ⑩ )アミノ酸と呼ぶ。
⑧ システイン
⑨ メチオニン
⑩ 必須

硫黄を含むアミノ酸は「サッカー(S)はメッシ」
必須アミノ酸は「風呂場の椅子を独り占め」!
詳しくはAZARASHIのブログで勉強しましょう(*^▽^*)
ヌクレオシドは糖と( ⑪ )から構成される。ヌクレオシドにリン酸が付加した生体分子を( ⑫ )と呼ぶ。DNA に固有な( ⑪ )は( ⑬ )、RNA に固有な( ⑪ )は( ⑭ )である。( ⑬ )と( ⑮ )が相補対を形成できる。
⑪ 塩基
⑫ ヌクレオチド
⑬ チミン
⑭ ウラシル
⑮ アデニン

「ヌクレオシド」と「ヌクレオチド」は、ただの言い間違えじゃない!
・糖+塩基 =ヌクレオシド
・糖+塩基+リン酸=ヌクレオチド
問2(計15点)
2.アルコール脱水素酵素によるエタノール酸化反応の化学反応式を示せ。また、この反応について、以下の語を全て用いて3行程度で説明せよ。用いた語には下線を引くこと。
[肝臓 電子受容体 触媒 補酵素 アセトアルデヒド]
CH3CH2OH+NAD+ → CH3CHO+NADH+H+
アルコール脱水素酵素は、アルコールからアルデヒドへの酸化反応を触媒する酵素である。ヒトの場合、肝臓に多く存在する。NAD+はアルコール脱水酵素の補酵素として働き、電子受容体の役割を担っている。

化学式を書かせる問題も出るのか…
問3(計15点)
3.I 型トポイソメラーゼの反応と生理機能、並びにカンプトテシン誘導体による反応阻害機構について、以下の語を全て用いて5行程度で説明せよ。用いた語には下線を引くこと。
[DNA 切断 ねじれ アポトーシス 中間体 DNA 複製]
I型トポイソメラーゼの反応は、主にDNAの複製や転写の際に生じるよじれの問題を緩和する働きを担う。2本鎖DNAのうち一方を切断することで、その切れ目の間をもう一方の鎖が通過しリンキング数が一つ変化する。切断部位は自然に再生し、ATPを要求しない。カンプトテシンはI型トポイソメラーゼ・DNA複合体と結合することでDNAの再生を妨げ、その結果としてDNAがアポトーシスを引き起こす。カンプトテシンは著しい抗がん活性があるため、この物質の利点を引き延ばす誘導体が数多く作られている。

もうムズすぎ…
問4(計20点)
4.以下に示す生物化学の実験技術に関して、その原理と使用目的を5行程度で説明せよ。
(1) ウエスタンブロット法
ウエスタンブロット法は、電気泳動によって分離したタンパク質を膜に転写し、任意のタンパク質に対する抗体でそのタンパク質の存在を検出する手法である。電気泳動の高い分離能と抗原抗体反応の高い特異性を組み合わせた手法であるため、細胞抽出液などの複雑なタンパク質溶液中に微量に含まれるタンパク質でも明瞭に検出することができる。特に不溶性のタンパク質、標識が困難なタンパク質、容易に分解されて免疫沈降法などに適応不可能なタンパク質を取り扱う場合に有効である。

最もポピュラーな実験法の一つ。
最初にDNAを検出する「サザンブロット法」を考案したのは、エドウィン・サザンさん。
RNAを検出する「ノザンブロット法」とタンパク質を検出する「ウエスタンブロット法」がユーモアで名づけられたという話は伝説。
(2) サンガー法による塩基配列決定法
サンガ―法とは、DNA合成の材料として取り込まれるとDNAの伸長が止まる4種類のジデオキシリボヌクレオシド三リン酸(ddATP、ddGTP、ddCTP、ddTTP)を用いた塩基配列決定法である。配列を決定したいDNAにジデオキシリボヌクレオシド三リン酸いずれか1種類を加え4つのDNA合成を行う。各反応では配列の異なる位置で伸長が止まった一連の産物ができる。この4つの反応産物を4つのレーンに並べてポリアクリルアミドゲル電気泳動で展開し、ゲルの下から順にすべてのレーンにわたってバンドを読み取る。

2018年度に出題された問題と同じ!
2018年度の過去問も合わせてご参照ください。
問5(計20点)
5.脂肪酸の代謝に関する以下の問いに答えよ。
(1) 酸化について、以下の語を全て用いて5行程度で説明せよ。用いた語には下線を引くこと。
[アセチル CoA 脂肪酸アシル CoA 位]
β酸化とは、脂肪酸を酸化して脂肪酸アシルCoAを生成し、そこからアセチルCoAを取り出す代謝経路のことである。β酸化は4つの反応の繰り返しから成り、一順するごとにアセチルCoAが1分子生成され、最終産物もアセチルCoAとなる。脂肪酸アシルCoAのβ位において段階的な酸化が行われることからβ酸化と名付けられた。脂肪酸の代謝の3つのステージ(β酸化、クエン酸回路、電子伝達系)の最初のステージであり、動物細胞では脂肪酸からエネルギーを取り出すための重要な代謝経路である。

脂肪酸は、脂肪酸アシルCoAになってからミトコンドリアに運ばれ、β酸化
これもAZARASHIさんのブログで勉強しましょう(/・ω・)/
(2) CH3(CH2)16COOH(ステアリン酸)が 酸化系で C2 単位まで分解される際の化学反応式を書け。物質は以下の記号で表すこと。
[AMP ATP CoA FAD FADH2 H+ H2O NAD+ NADH PPi]
CH3(CH2)16COOH + HS-CoA + ATP
→ CH3(CH2)16 COS-CoA + H2O + AMP +PPi
CH3(CH2)16 COS-CoA + 8FAD + 8NAD + 8HS-CoA
→ 9CH3COOS-CoA + 8FADH2+8NADH +8H+

む、難しい…
この反応式は自信ない。
ちなみに、C2単位とはアセチルCoAのことです。
問題を解き終えた感想
【2016年度の特徴】
- the 生化学の問題が多い印象
- 化学反応式の問題が出た
- ムズすぎ…
他年度の問題を解いてきた印象として「生物化学」といいつつ「分子生物学」の問題が多い印象でしたが、2016年度に関しては「The 生物化学」の問題が多い印象でした。
ボクのバックグラウンドによるものかもしれませんが、今回はめちゃくちゃ難しい!!
ここまで化学よりの問題が出ると全く歯が立たないです(/o\)
特に、β酸化の反応式は鬼ですね…

化学反応式を問う問題はかなりレアなので、無理して覚える必要はないかも
2016年度の派生問題
代表的な六単糖のアルドースといえば、グルコース、マンノース、ガラクトースであるが、代表的な五単糖のアルドースといえば、(①)、(②)、(③)である。(①)はヌクレオチドの構成成分として知られ、(②)と(③)は植物に豊富に含まれる成分として知られる。自然界においては、(②)はD体よりもL体が多く存在する一方、(③)はD体のみが存在し、L体は有機化学合成によって作られる。
① リボース
② アラビノース
③ キシロース

五単糖のケトースといえば、リブロースとキリルロースか…これを暗記していってもキリがないな〜
脂肪酸は構造の違いから(①)脂肪酸と(②)脂肪酸に分類され、炭化水素の尾部に二重結合があるものを(①)脂肪酸、二重結合をもたないものを(②)脂肪酸とよぶ。(①)脂肪酸は同じ炭素数の(②)脂肪酸と比べて融点が(③)い。
① 不飽和
② 飽和
③ 低

飽和脂肪酸は、乳製品や肉などの動物性脂肪に多く含まれ、パルミチン酸、ステアリン酸など。
一方、不飽和脂肪酸は植物脂に多く含まれ、オレイン酸、リノール酸などがある。
過去問リンク
- 2023年度の過去問(生物化学)
- 2022年度の過去問(生物化学)
- 2021年度の過去問(生物化学)
- 2020年度の過去問(生物化学)
- 2019年度の過去問(生物化学)
- 2018年度の過去問(生物化学)
- 2017年度の過去問(生物化学)
- 2016年度の過去問(生物化学)
- 2015年度の過去問(生物化学)
- 2014年度の過去問(生物化学)
- 2013年度の過去問(生物化学)
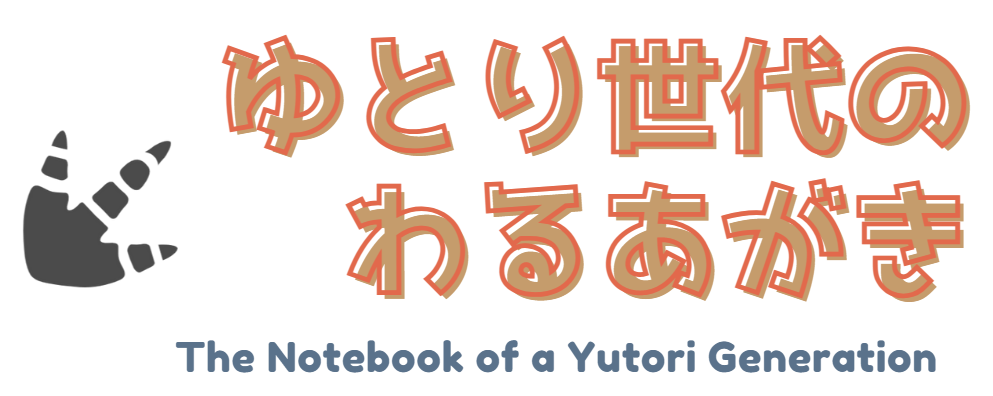
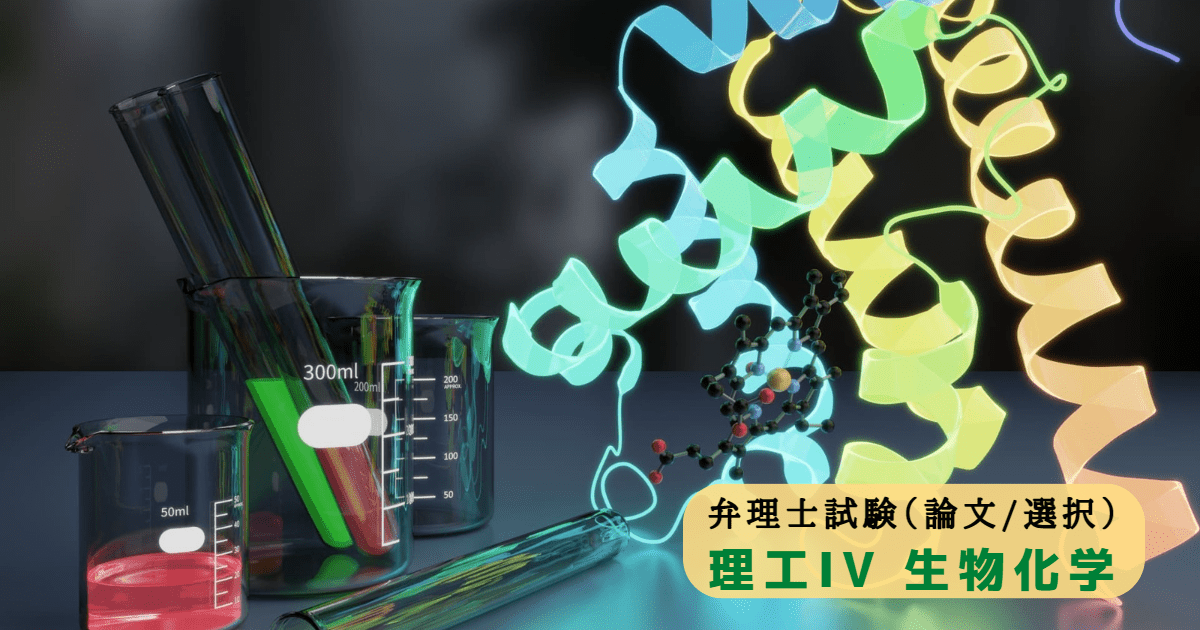




Comment