二次試験(論文/選択科目)の対策!
特許庁のWebサイトで公開されている過去問の中から、理工IV(生物)の「生物化学」を解いてみました。
今回は、2014年度(令和26年)の問題です。
ボクなりの回答と、ボクが考えた派生問題を共有させていただきます。

おかしな箇所があれば、Comment欄にてご指摘ください。
2014年度の過去問
問1(計20点)
1.以下は DNA に関する一連の研究について述べたものである。空欄( ① )から( ⑩ )に適当な語を入れよ。ただし、同じ番号には同じ語が入り、①、②、⑥は同位元素を表す。
1952 年にハーシーとチェイスは、T2 バクテリオファージの DNA を( ① )、タンパク質を( ② )でそれぞれ標識し、いずれの生体成分が子孫ファージへと伝達されるかを調べた。その結果、( ① )標識が子孫ファージへ伝達されることを示し、DNA が遺伝情報伝達物質であるという証拠を得た。
① P32
② S35

これは簡単♪
生物の設計図である『遺伝子』。当時は「タンパク質」が遺伝子の担い手だと考えられていたのですが、ハーシーとチェイスの実験により「タンパク質」ではなく「DNA」が遺伝子の担い手であることが証明されました。
1953 年にワトソンとクリックは( ③ )モデルを構築し、アデニンと( ④ )、グアニンと( ⑤ )が水素結合を形成して塩基対を形成していることを提唱した。
③ 二重らせん
④ チミン
⑤ シトシン

これも簡単!
生物の設計図が「DNA」であることが証明された後、ワトソンとクリックによってDNAの構造(二重らせん構造)が提唱されました。このあまりにも美しくシンプルな事実は、世界を驚かせたそう。
1958 年にメセルソンとスタールは、同位元素を用いた実験から DNA 複製の際に( ③ )が分離することを示した。すなわち、第一世代として( ⑥ )を含む培地で菌を生育させて DNA を( ⑥ )で標識した。次に、( ⑥ )を含まない培地で菌を生育させて第二世代と第三世代の菌を増殖させた。最後に、菌から抽出した DNA を( ⑦ )法で分離した。その結果、第一世代の DNA は比重が重く、第二世代は中間の比重を示し、第三世代は中間の比重と軽い比重の DNA となっていた。これら一連の実験から、DNA は( ⑧ )的複製をしていることが示された。
⑥ N15
⑦ 遠心
⑧ 半保存

ワトソンとクリックが提唱した「DNAの半保存的複製」を証明したのはメセルソンとスタール
DNA はタンパク質合成の直接の鋳型とはならず、仲介分子として( ⑨ )を合成するための鋳型として働いている。( ⑨ )を合成する反応を( ⑩ )反応と呼ぶ。
⑨ mRNA
⑩ 転写
問2(計30点)
2.ES 細胞と iPS 細胞について、以下の問いに6行程度で答えよ。
(1) ES 細胞と iPS 細胞の作製方法を説明せよ。
ES細胞は、受精卵が胚盤胞と呼ばれる段階まで発生したところで内部細胞塊を取り出し、フィーダ細胞という下敷きとなる細胞と一緒に培養することで作成される。一方、iPS細胞は、レトロウイルス・ベクターを使って4つの遺伝子(Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Myc)を体細胞に導入することで作成される。レトロウイルス・ベクターは、腫瘍形成のリスクを伴うため、iPS細胞樹立後に導入遺伝子を除去する方法や、アデノウイルス・ベクター、センダイウイルス、プラスミドDNAを用いた誘導法が利用されることもある。

ざっくり書くと3行程度で終わっちゃうからレトロウイルス・ベクターと腫瘍形成のリスクをいれてみたけど…どうだろう。
(2) ES 細胞に対する iPS 細胞の利点を論ぜよ。
ヒトES細胞を作成するには「生命の萌芽」と位置付けられるヒト受精卵の破壊を伴うことから倫理的な問題があるとされていた。また、細胞移植治療に応用する際、患者とは他人の細胞であることから、免疫拒絶反応が惹起されてしまう可能性が高い。一方、iPS細胞は体細胞から作られるため、倫理的な問題には該当せず、患者さん自身の細胞から作成することができるため、分化した組織や臓器の細胞を移植する際、拒絶反応が起こりにくいと考えられている。

ちょっと文字数が少ないかも。
iPS細胞の利点は大きく2点
- 倫理的な問題を回避できる
- 免疫拒絶反応が起こりにくい
問3(計20点)
3.DNA の超らせん構造の変換を触媒する酵素として DNA トポイソメラーゼが知られている。DNA トポイソメラーゼはⅠ型とⅡ型に大別されるが、両者の違いを5行程度で論ぜよ。
I型トポイソメラーゼはDNAの二本鎖のうち一本だけを切断する。その切れ目の間をもう一方の鎖が通過した後、切れ目を再結合することでリンキング数を一つ変化させる。主にDNAの複製や転写の際に生じるDNA超らせんを緩和する働きをもつ。一方、II型トポイソメラーゼはDNA二本鎖を切断する。その切れ目の間を別の二本鎖が通過した後、切れ目を再結合することでリンキング数を二つ変化させる。DNA超らせんの緩和に加えて、複製後に生じるDNA間の絡まりの解消を担う。

トポイソメラーゼは、「抗がん剤」や「抗菌薬」のターゲットとして知られる
問4(計30点)
4.生物化学に関する以下の実験技術について、原理と使用目的を5行程度で説明せよ。
(1) ウエスタンブロット法
ウエスタンブロット法は、電気泳動によって分離したタンパク質を膜に転写し、任意のタンパク質に対する抗体でそのタンパク質の存在を検出する手法である。電気泳動の高い分離能と抗原抗体反応の高い特異性を組み合わせた手法であるため、細胞抽出液などの複雑なタンパク質溶液中に微量に含まれるタンパク質でも明瞭に検出することができる。特に不溶性のタンパク質、標識が困難なタンパク質、容易に分解されて免疫沈降法などに適応不可能なタンパク質を取り扱う場合に有効である。

2016年度に出題された問題と全く同じ!
(2) DNA マイクロアレイ法
DNAマイクロアレイ(DNAチップ)とは、数万から数十万に区切られた基板上に塩基配列の明らかな1本鎖のDNAを高密度に配置して固定したものを指す。検体から抽出した遺伝子と基準となる標準検体を別々の蛍光色素で標識した後、DNAチップとハイブリダイゼーション反応をさせる。反応後、洗浄したDNAチップをスキャナーで読み取り、抽出した遺伝子と基準となる標準検体のシグナルの比を調べることにより、どのような遺伝子がどの程度発現しているかを調べることができる。

DNAマイクロアレイってよく耳にするけど、全く理解できてなかった…
問題を解き終えた感想
【2014年度の特徴】
- 分子生物学に関する問題が中心
- 「穴埋め問題」、「説明問題」どちらも解きやすい問題が多い
2014年度は、分子生物学の歴史に関する問題が印象的でした。
高校レベルの知識で回答できる問題が多く、この試験を受けた受験生は大当たり!
2015年度がめちゃくちゃ難しかったので、

過去に遡るほど難しい???
とか考えていましたが、そんなんことはないようですね。
生物化学の難易度は運次第…( ;∀;)
ちなみに、分子生物学の歴史を楽しく学ぶならこの本。
2014年度の派生問題
1928年、グリフィスは病原性をもつS型と病原性をもたないR型、2種類の(①)菌を用いて、バクテリアにおける(②)を発見した。これによって、遺伝情報が転移できることが示唆された。
① 肺炎双球菌
② 形質転換
グリフィスの実験以後、マウスに注射をしなくても、生きたR型菌を死んだS型菌と混ぜて培養するだけで形質転換がおこることがわかった。そして1944年、アベリーはS型菌の成分を( ① )の分解酵素や( ② )の分解酵素で処理をしても形質転換がおこるが、( ③ )の分解酵素で処理をすると形質転換がおこらなくなることを発見した。これによって、( ③ )が遺伝情報伝達物質であることが示唆された。
① タンパク質
② RNA
③ DNA
この時代、遺伝情報伝達物質はタンパク質だと考えられていたため、アベリーの発見は、当時の常識を覆す驚きの大発見でした。
しかし、この実験では、「分解しきれていないタンパク質が形質転換に関与したのでは?」とする主張を完全に覆すことができず、ハーシーとチェイスの実験によって、証明されることとなります。
ES細胞を用いたノックアウトマウスの作り方を説明せよ
まずノックアウトしたい遺伝子を確定し、ゲノムライブラリーの情報に基づいてターゲティングベクターを作成する。次いで、ターゲティングベクターをエレクトロポレーション法でES細胞に導入した後、相同組み換えが起きたES細胞を単離する。相同組み換えが起きたES細胞を胚盤胞にインジェクションし、マウスの子宮に入れるとキメラマウスが産まれる。このキメラマウスはノックアウトしたい遺伝子が欠損した細胞と正常な野生型の細胞を併せ持っている。キメラマウスと野生型のマウスを交配することで、完全に遺伝子が欠損したマウスを作成することができる。

今ではCRISPR-Cas9を応用したノックアウトマウスの作成法が主流になりつつあるとか。
CRISPR-Cas9を応用したノックアウトマウスの作成法はこちらの派生問題をご参照ください。
過去問リンク
- 2024年度の過去問(生物化学)
- 2023年度の過去問(生物化学)
- 2022年度の過去問(生物化学)
- 2021年度の過去問(生物化学)
- 2020年度の過去問(生物化学)
- 2019年度の過去問(生物化学)
- 2018年度の過去問(生物化学)
- 2017年度の過去問(生物化学)
- 2016年度の過去問(生物化学)
- 2015年度の過去問(生物化学)
- 2014年度の過去問(生物化学)
- 2013年度の過去問(生物化学)
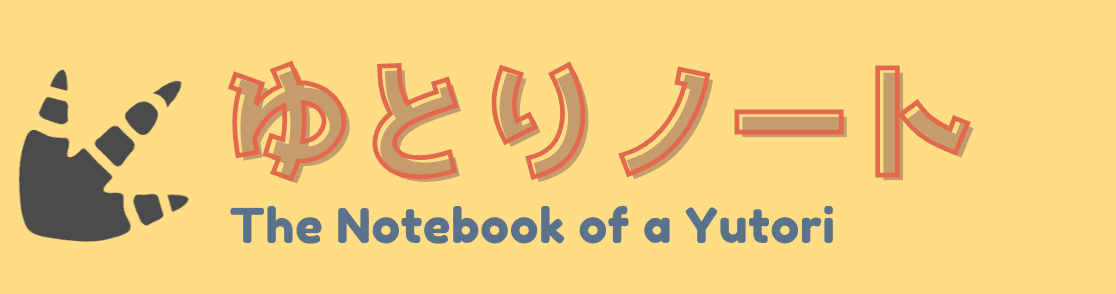
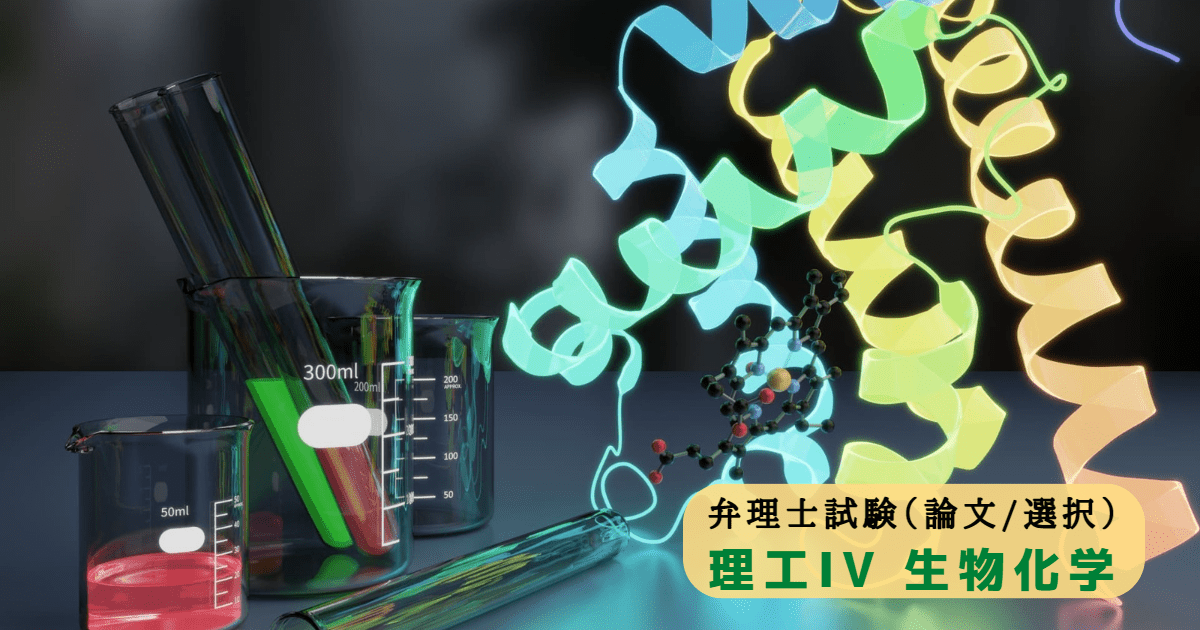




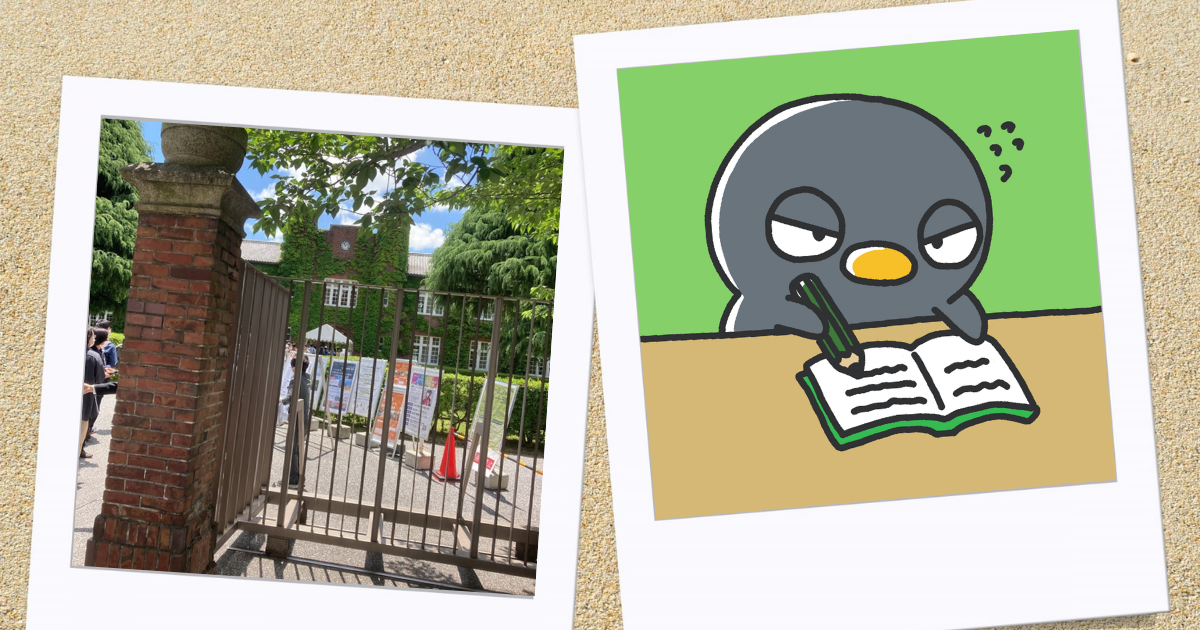
Comment
こんにちは、弁理士試験を受験しているものです。
2次試験で選択科目を受験しなければならないにもかかわらず、必須試験の論文対策で全く手をつけられていなかったので、ここ3週間ほどこちらのサイトを活用させてもらっておりました。
生物系の大学を出ているのですが、大学院まで行っておらず、卒業からかなり経ち、ほぼ忘れていることが多かったのでとても参考になりました。ありがとうございました。
今日、過去問で出た実験手法出題されろ…!と念じながら受けてきましたが、なんだか不合格なような気がしています…。
ataruさんも勉強を続けられるのでしょうか。陰ながら応援しております。
とろろさん、コメントを頂きありがとうございます♪♪少しでもお役に立てたようで嬉しいです(ToT)
今年は意外な問題が出たそうですね…
出題範囲が広さといい、問題の難易度といい、本当に難しい試験です(;_;) 吉報をお祈りします(*>人<) ノロノロペースではありますが、ボクも弁理士の勉強を続けています。一緒に頑張りましょう♪