二次試験(論文/選択科目)の対策!
特許庁のWebサイトで公開されている過去問の中から、理工IV(生物)の「生物化学」を解いてみました。
今回は、2018年度(平成30年)の問題です。
ボクなりの回答と、ボクが考えた派生問題を共有させていただきます。

おかしな箇所があれば、Comment欄にてご指摘ください。
2018年度の過去問
問1(計40点)
1 生物化学に関する以下の事項について、空欄の( ① )から( ⑳ )に適切な語 を入れよ。ただし、同じ番号には同じ語が入る。
DNA 上の遺伝情報は、( ① )へ転写され、( ① )を鋳型としてタンパク質を合成することで発現する。( ① )からタンパク質を合成する反応を( ② )と呼ぶ。真核生物の( ① )の大部分は 5´末端に( ③ )、3´末端にポリ A 尾部を持つ。これらの構造は( ① )の安定性と( ② )活性を増強する。( ② )反応は、( ④ )と呼ばれる巨大分子複合体中で起きる。( ④ )中の活性中心は、( ⑤ )分子が形成しており、触媒( ⑤ )の好例である。( ② )反応で合成されたタンパク質が酵素などとして働く。
① メッセンジャーRNA
② 翻訳
③ キャップ
④ リボソーム
⑤ ぺプチジルtRNA?

⑤はちょっと自信ない…
ある種の酵素は、合成された後、一箇所若しくは複数箇所のアミノ酸配列が切断されることで活性化される。切断前の不活性なタンパク質を( ⑥ )と呼ぶ。例えば、ウシのキモトリプシンは、不活性な( ⑦ )として( ⑧ )で合成された後、小腸に運ばれ、15 番目のアルギニンと 16 番目のイソロイシンの間の( ⑨ )結合が( ⑩ )によって切断されることで活性型となる。( ⑩ )は、代表的なセリンプロテアーゼであり、セリンの( ⑪ )基が活性中心を形成している。この( ⑪ )基が標的となる( ⑨ )結合中の( ⑫ )を求核攻撃し、( ⑬ )反応によって( ⑨ )結合を切断する。( ⑨ )結合の炭素-( ⑭ )結合は、共鳴構造によって部分的な( ⑮ )を有する。そのため、比較的強い結合となる。さらに、( ⑨ )結合中の( ⑫ )原子は、カルボン酸エステル化合物中の( ⑫ )原子よりも求核性が弱く、求核攻撃を受けにくい。そのため、非酵素的な( ⑬ )反応が起きにくい。
⑥ 前駆体
⑦ キモトリプシノーゲン
⑧ 膵臓(の腺房細胞)
⑨ ペプチド
⑩ エンテロペプチダーゼ
⑪ セリン残
⑫ カルボニル炭素
⑬ 開裂
⑭ 窒素
⑮ 二重結合

これも難しい…
いくら調べても自信がないので、詳しい方がいらっしゃいましたらコメントお願いします(>_<)
⑥の答えを「前駆体」としましたが、「切断前の不完全な酵素」であれば「チモーゲン」…かな?
酵素による( ⑯ )作用は、自発的反応である。この自発的反応が起きるためには、( ⑰ )エネルギーが減少する必要がある。( ⑰ )エネルギーは、反応の自発性に関する情報を与えるが、酵素反応の速度についての情報は与えない。反応速度は、( ⑱ )エネルギーに依存する。酵素は反応速度を速めるが、反応の( ⑲ )点は変えられない。したがって、反応における酵素の有無によって最終的な生成物の量は変わらない。酵素が反応を加速させる機構は、化学反応の( ⑳ )の形成を容易にすることで説明される。
⑯ 触媒
⑰ 自由
⑱ 活性化
⑲ 開始
⑳ 遷移状態
酵素の反応速度に関する問題は、大学1年で習いましたが、計算問題が多く難しいです。
突っ込んだ問題が出ないことを祈るばかり(人ω<`;)
問2(計20点)
2 タンパク質と脂質に関する以下の問いに答えよ。
(1) 26S プロテアソームによるタンパク質の分解について、以下の語をすべて使って5行程度で説明せよ。なお、用いた語には下線を引くこと。
[ATP、ユビキチン、ユビキチンリガーゼ、20S、調節ユニット]
26Sプロテアソームはプロテアーゼ活性をもつ20Sとその調節ユニットからなる。20Sは中空円筒構造を持ち、細胞内のタンパク質と空間的に隔離されている。調節ユニットは、折りたたみの誤りなど何らかの異常があるためユビキチンリガーゼとユビキチン結合酵素によってユビキチン鎖が付加されたタンパク質と選択的に結合する。その後、ATP加水分解を利用してそのタンパク質のポリペプチド鎖をほどいた上で、20Sの内部に送り込む。20Sの内部に送り込まれたタンパク質は、短いペプチドに分解された後,20Sの外部に放出される。

全く覚えてない…
一から調べなおし…
(2) リン脂質の構造と機能について、以下の語をすべて使って5行程度で説明せよ。なお、用いた語には下線を引くこと。
[生体膜、グリセロール、スフィンゴシン、二重膜構造、疎水性]
一般的なリン脂質はグリセロールやスフィンゴシンを中心骨格として脂肪酸とリン酸が結合し、さらにリン酸にアルコールがエステル結合した構造をもつ。構造中に疎水性の脂肪酸エステル部位と親水性のリン酸アニオン部位が共存するため、リン脂質は界面活性剤のような両新媒性を示し、水中では外側に親水性部を向けて疎水性部同士が集まり二重膜構造を形成する。この構造は生体膜として利用されており、内部の物質の拡散を防ぐとともに、イオンポンプを有することで塩濃度やpHを調整することができる。
問3(計40点)
3 生物化学の実験技術に関する以下の問いに答えよ。
(1) ミエローマ細胞(骨髄腫細胞)を用いたモノクローナル抗体の作製法について、5行程度で説明せよ。
まず目的の抗原でマウスを免疫し、その抗原を特異的に認識する抗体を生産するB細胞を増殖させる。次いで、そのマウスの脾臓もしくはリンパ節からB細胞を取り出す。B細胞の寿命は有限であるため、ミエローマ細胞と融合させることで無限に増殖する能力を合わせもつハイブリドーマを作成した後、1細胞単位で単離培養する。一つのB細胞からは一種類のエピトープを認識する抗体しか作られないため、ハイブリドーマを1細胞単位で単離した培地はモノクローナル抗体の安定かつ永続的な供給源となる。

やっと解きやすい問題がきた!
1984年にノーベル賞が授与されることとなったハイブリドーマの技術です。現在医療の最前線で活躍する「抗体医薬」の誕生に大きく貢献するとともに、実験手法としても大活躍しています。
(2) ポリクローナル抗体とモノクローナル抗体の違い、及び抗体を用いた実験技術の例について、5行程度で説明せよ。
1つの抗体は1種類のエピトープを認識する。一般的に、動物を目的の抗原で免疫して得られる抗体には、目的の抗原の様々なエピトープを認識する抗体が混合しており、これをポリクローナル抗体という。一方、抗体の認識部位が同じになるように、単一の抗体産生細胞をクローニングして作られたものをモノクローナル抗体という。ELISA法では抗体を用いて、試料溶液中に目的の抗原が含まれるかどうか検出・定量することができる。
ヒトや動物に抗原を投与して得られる抗血清には、抗原の様々な部位と結合する抗体が混じっているためポリクローナル抗体といいます。
これに対して、単一の抗体産生細胞をクローニングして、一種類の抗体だけにしたものをモノクローナル抗体といいます。

ボクが学生時代聞いた話では、モノクローナル抗体の作成を外注すると100万&3~6ヶ月かかるとか…
(3) 薄層クロマトグラフィー法について、5行程度で説明せよ。
薄層クロマトグラフィー法は、液体クロマトグラフィーの一種で、低コストかつ手軽な分析法として知られている。ガラス板やアルミシートなどの表面にシリカゲル、アルミナもしくはポリアミド樹脂などを添付した薄層板を試料溶液中に立てかけるように入れる。溶媒は毛細管現象によって薄層に浸み込み上昇していき、展開が開始される。試料を分離した結果は、溶媒の移動距離と求めたい物質の移動距離の相対値(Rf値)を求めて評価する。

クロマトグラフィーといえば、これだよね。
(4) デオキシ法(サンガー法)による DNA 塩基配列決定法について、7行程度で説明せよ。
まず塩基配列を決定したい二本鎖DNAを一本鎖DNAに分離する。次いでDNA鎖の伸長を止める4種類のジデオキシリボヌクレオシド三リン酸((ddATP、ddCTP、ddGTP、ddTTP))をいずれか一種類ずつ加え、先ほどの一本鎖DNAを鋳型として別個に4つの合成を行う。各反応では配列の異なる位置で伸長が止まった一連の産物ができる。この4つの反応産物を4つのレーンに並べてポリアクリルアミドゲル電気泳動で展開する。プライマーあるいはデオキシリボヌクレオシド三リン酸に取り込ませておいた標識を検出すると、各レーンにはいずれかのヌクレオチドについて、DNAの異なる部位で伸長が止まった一連の断片のバンドが現れる。ゲルの下から順にすべてのレーンにわたってバンドを読み取ると新しく合成されたDNAの塩基配列が決定できる。

DNA配列を調べる古典的な実験法といえば「サンガー法」と「マキサム・ギルバート法」。近年は次世代シークエンサーの普及が進み引退しつつあるそう。
「次世代シークエンサー」については、製品によって原理が異なるため、
- 一塩基ごとの伸長反応を検出し塩基配列を決定すること
- 電気泳動を必要としないこと
- 一度に膨大な塩基配列の解析が可能であること
をおさえておきましょう。
問題を解き終えた感想
【2018年度の特徴】
- 「穴埋め問題」、「説明問題」どちらも難しい!
- 出題傾向として、「生物化学」寄りの問題が多い印象
- 穴埋め問題の配点が高い
2018年度の問題は、めちゃくちゃ難しい‼︎
参考書を持ち込んでも、合格できないかもしれません…
年度によって難易度にバラツキがあるようですので、ここまで難しい問題に当たってしまったら、運が悪かったと諦めるしかないかもしれませんね〜(。-∀-)
2018年度の派生問題
有名なセリンプロテアーゼとして「トリプシン」、「キモトリプシン」、「エラスターゼ」の3種類が知られ、小腸におけるペプチド消化の大半を触媒している。これら3種類のセリンプロテアーゼは不活性な前駆体として膵臓で貯蔵されているが、それぞれの前駆体の名前は?
トリプシンの前駆体:トリプシノーゲン
キモトリプシンの前駆体:キモトリプシノーゲン
エラスターゼの前駆体:プロエスターゼ
化学反応は「自由エネルギー」に依存する。この「自由エネルギー」は「G」と表記するが、反応時に起こる「自由エネルギー変化」をどのように表記するか?
ΔG(デルタG)

「A+B→C+D」という反応があったとすると、「ΔG = (C+D)のエネルギー - (A+B)のエネルギー」。つまりΔGがマイナスであれば反応が起こりやすいということ。
マキサム・ギルバート法による塩基配列決定法について説明せよ。
塩基配列を決定したい二本鎖DNAを一本鎖DNAに分離した上で、5’末端を放射性リンで標識する。次いで、4種類の塩基特異的なDNA切断溶液をいずれか一種類ずつ加え、DNA断片の切断を行う。この4つの反応産物を4つのレーンに並べてポリアクリルアミドゲル電気泳動で展開すると断片のサイズごとに分離される。最後にオートラジオグラムにかけてバンドを下から読み取っていくことでDNAの塩基配列を決定できる。

操作が煩雑だったり、危険な試薬を使うからサンガー法の方がメジャーだけどね。
過去問リンク
- 2024年度の過去問(生物化学)
- 2023年度の過去問(生物化学)
- 2022年度の過去問(生物化学)
- 2021年度の過去問(生物化学)
- 2020年度の過去問(生物化学)
- 2019年度の過去問(生物化学)
- 2018年度の過去問(生物化学)
- 2017年度の過去問(生物化学)
- 2016年度の過去問(生物化学)
- 2015年度の過去問(生物化学)
- 2014年度の過去問(生物化学)
- 2013年度の過去問(生物化学)
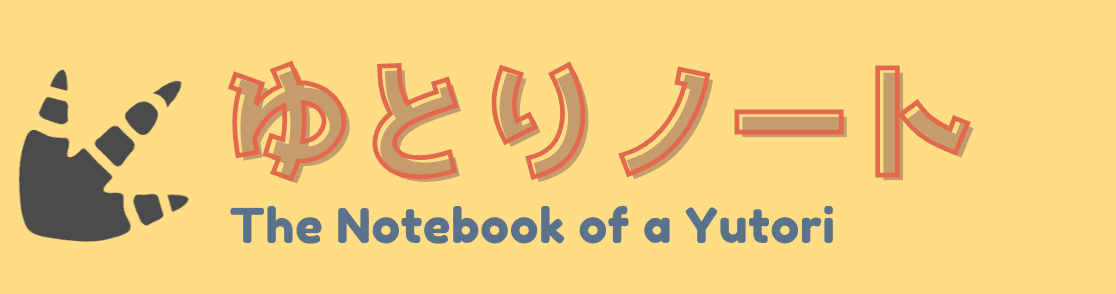
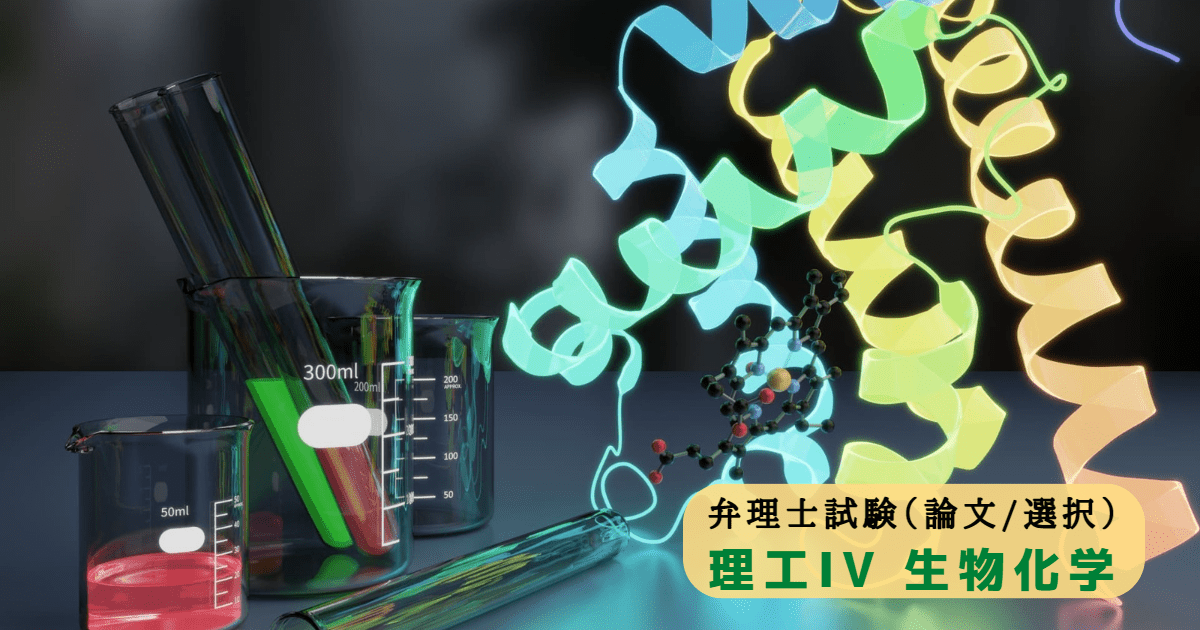


Comment