二次試験(論文/選択科目)の対策!
特許庁のWebサイトで公開されている過去問の中から、理工IV(生物)の「生物化学」を解いてみました。
今回は、2021年度(令和3年)の問題です。
ボクなりの回答と、ボクが考えた派生問題を共有させていただきます。

おかしな箇所があれば、Comment欄にてご指摘ください。
2021年度の過去問
問1(計40点)
1 以下の事項について、空欄の( ① )から( ⑳ )に適切な語を入れよ。ただし、同じ番号には同じ語が入る。
(1) 細胞は細胞周期と呼ばれる規則的な過程を繰り返し増殖する。細胞周期はまず大きく( ① )期と間期に分けられる。間期は更に( ② )期(DNA の合成準備期)、( ③ )期(DNA 合成期)、( ④ )期 (分裂準備期)に分けられる。細胞周期を進行させる細胞周期エンジンとして機能する複合体は( ⑤ )と( ⑤ )依存性キナーゼから構成され、( ⑤ )は細胞周期特異的に発現するタンパク質として発見された。
① M期
② G1
③ S
④ G2
⑤ サイクリン

M期に「有糸分裂」と「細胞質分裂」が行われる。
それと…サイクリン依存タンパクキナーゼは「Cdk」。
(2) 酵母などにおける( ⑥ )発酵ではピルビン酸が2段階の反応で( ⑦ )に変換される。この反応ではまずピルビン酸から二酸化炭素が外され、ピルビン酸は炭素2個の( ⑧ )に変換される。次に( ⑧ )は NADH によって還元されて( ⑦ )になる。一方、ヒトの筋肉などの組織における嫌気呼吸ではピルビン酸は直接 NADH によって還元され、最終産物として( ⑨ )を生じるが二酸化炭素は発生しない。生成した( ⑨ )は( ⑩ )回路によって肝臓で再びピルビン酸に戻される。
⑥ アルコール
⑦ エタノール
⑧ アセトアルデヒド
⑨ 乳酸
⑩ コリ

たしか…ヒトにおける乳酸の経路は、酸素が不足している状況でのエネルギー生成手段として利用されていて、運動すると乳酸が溜まるんだっけ…?
【アルコール発酵】
グルコース→2ピルビン酸
C6H12O6 + 2NAD+ + 2ADP + 2H3PO4 → 2CH3COCOOH + 2NADH + 2H+ + 2ATP + 2H2O
2ピルビン酸→2アセトアルデヒド
2CH3COCOOH → 2CH3CHO + CO2
2アセトアルデヒド→2エタノール
2CH3CHO + 2NADH +2H+ → 2CH3CH2OH + 2NAD+
【乳酸発酵】
グルコース→2ピルビン酸
(省略)
ピルビン酸→乳酸
2CH3COCOOH + 2NADH +2H+ → 2CH3CH(OH)COOH + 2NAD+
(3) 酵素は生体( ⑪ )として機能する分子である。酵素は無機( ⑪ )と同じように、化学反応の( ⑫ )を増加させるが反応物と生成物の( ⑬ )に影響しない。これは反応の出発物質を( ⑭ )状態に励起するのに必要な( ⑮ )エネルギーを( ⑯ )させ反応を促進することを意味している。
⑪ 触媒
⑫ 速度
⑬ 結果
⑭ 遷移(せんい)
⑮ 活性化
⑯ 低下

⑬はちょっと自信ない。
有名な無機触媒といえば、過酸化水素水の分解を促進する「二酸化マンガン」。
生体触媒と無機触媒の違いは最適温度&最適pHがあるかどうかです。
(4) アミノ酸は様々な生理活性物質の原料となっている。ドーパミンの前駆体である Lドーパは( ⑰ )の水酸化によって作られる。ヒスタミンは( ⑱ )、GABA と呼ばれる γ-アミノ酪酸は( ⑲ )、セロトニンは( ⑳ )を前駆体アミノ酸として生合成される。
⑰ チロシン
⑱ ヒスチジン
⑲ グルタミン酸
⑳ トリプトファン
・チロシン ⇒ L-ドーパ ⇒ ドーパミン
・ヒスチジン ⇒ ヒスタミン
・グルタミン酸 ⇒ GABA
・トリプトファン ⇒ セロトニン
問2(計10点)
2 生物化学に関する以下の問いに答えよ。
ある 8.0 kbp の環状 DNA を制限酵素 HindIII で切断すると 3.0 kbp と 5.0 kbp の DNA 断片が得られた。同じ環状 DNA を制限酵素 HindIII と EcoRI で同時に切断すると 4.0 kbp、2.5 kbp、1.0 kbp、0.50 kbp の DNA 断片が得られた。この環状 DNA を EcoRI だけで切断するとどのような大きさの DNA 断片が得られると考えられるか。すべてのパターンを記せ。(kbp:kilobase pairs)
・1.5kbpと6.5kbp
・3.5kbpと4.5kbp

新しいタイプの問題!?
本番で出題されると焦るかもしれないけど、落ち着いて考えれば超サービス問題
HindIIIのみで切断した場合「2断片」、HindIIIとEcoRIで切断した場合「4断片」なので、EcoRIの切断部位は2箇所。
このうちEcoRIで得られる「5.0kbp⇒4.0kbpと1.0kbp」、「3.0kbp⇒2.5kbpと0.5kbp」といった具合に切断するってことですよね?
HindIIIとEcoRIで切断した場合の並びは4パターン
① 4.0kbp, 1.0kbp, 2.5kbp, 0.5kbp
② 1.0kbp, 4.0kbp, 2.5kbp, 0.5kbp
③ 4.0kbp, 1.0kbp, 0.5kbp, 2.5kbp
④ 1.0kbp, 4.0kbp, 0.5kbp, 2.5kbp
※ 直線ではなく円形に断片が並んでます
EcoRIのみで切断すると青と緑が繋がり、
① (0.5kbp+4.0kbp), (1.0kbp+2.5kbp) = 4.5kbp, 3.5kbp
② (0.5kbp+1.0kbp), (4.0kbp+2.5kbp) = 1.5kbp, 6.5kbp
③ (2.5kbp+4.0kbp), (1.0kbp+0.5kbp) = 6.5kbp, 1.5kbp
④ (2.5kbp+1.0kbp), (4.0kbp+0.5kbp) = 3.5kbp, 4.5kbp
よって、得られる断片は2パターン(「4.5kbp, 3.5kbp」 or 「1.5kbp, 6.5kbp」)
問3(計20点)
3 タンパク質 A とタンパク質 B との相互作用を検証したい。以下の実験技術を用いて検証する手順について6行以内で説明せよ。
(1) 共免疫沈降法
まずタンパク質Aに対する抗体を準備し、ビーズに結合させておく。これをタンパク質A及びタンパク質Bを含む溶液に加えると、タンパク質Aと抗体が複合体を形成し、ビーズ上に捕捉され沈殿回収できる。最後に、ビーズに結合したタンパク質を溶出し、ポリアクリルアミドゲル電気泳動で解析する。タンパク質Aとタンパク質Bとの相互作用がある場合、タンパク質Aだけでなくタンパク質Bも検出される。

タンパク質相互作用解析法は、生体内に近い環境で網羅的な検出ができる“in vivo法”と、再現性が比較的高くより直接的な相互作用解析ができる“in vitro法”に大別でき、共免疫沈降(Co-IP)は”in vitro法”に分類される。
[in vitro法]
- 共免疫沈降(Co-IP)
⇒ ネイティブな解析ができる - プルダウンアッセイ法
⇒ 抗体がなくても解析可能 - ファーウェスタンブロット法
⇒ ウエスタンを解析に応用 - 架橋反応法(クロスリンク法)
⇒ 結合の弱い解析に有効 - ラベル転移反応法
⇒ 結合の弱い解析に有効
相互作用部位を同定できる - 相互作用マッピング法
⇒ 相互作用部位を同定できる - 表面プラズモン共鳴法
⇒ リアルタイムで測定できる - 蛍光共鳴エネルギー移動法(FRET)
⇒ 蛍光分子で相互作用を解析
in vitro法の概要については、こちらの記事を参考にさせて頂きました。
(2) 酵母ツーハイブリッド法
まず組み換えDNA技術でタンパク質Aを指令するDNAの塩基配列を遺伝子活性化タンパクのDNA結合ドメインの指令領域と結合させる。一方、タンパク質Bを指令するDNAの塩基配列を遺伝子活性化タンパクの活性化ドメインの指令領域と結合させる。最後に、これらの融合タンパクを酵母の細胞内で発現させる。タンパク質Aとタンパク質Bが相互作用する場合は、遺伝子活性化タンパクの結合ドメインと活性化ドメインを含む複合体が形成され、レポーター遺伝子の転写が活性化する。

酵母ツーハイブリッドは、“in vivo法”の代表例。
共免疫沈降(Co-IP)では、相互作用するタンパク質の候補が決まっているときに用いられる一方、酵母ツーハイブリッドは、相互作用するタンパク質がよくわからず、未知のタンパク質をスクリーニングする目的で用いられる。
詳しくは、AZARASHIさんのブログをご参照ください。
問4(計30点)
4 次の対比する2つの語に関して違いが分かるように4~6行で説明せよ。
(1) ユビキチン・プロテアソームシステムとオートファジー
ユビキチン・プロテアソームシステムとは、ユビキチンが共有結合した標的タンパク質をプロテアソームが認識し選択的に分解するシステムのことをいう。不要タンパク質の分解、抗原提示、細胞周期調節など重要な役割を果たしている。一方、オートファジーは、細胞内部の不要物質をオートファゴゾームという膜で包み込み、リソソームと融合することで、それら不要物質を分解することをいう。ユビキチン・プロテアソームシステムはタンパク質を標的とするが、オートファゴソームはオルガネラなど大きなレベルで分解する。

簡単に説明しろっていわれるとめちゃくちゃ難しい…
「ユビキチン・プロテアソームシステム」はタンパク質を分解し、「オートファゴソーム」は侵入した微生物や損傷したオルガネラ(細胞小器官)などを分解する。
(2) 非相同末端結合修復と相同組換え修復
非相同末端結合修復は二本鎖切断されたDNA修復メカニズムの一つである。DNAの相同性とは無関係に切断された末端同士を直接繋ぎ合わせるため、姉妹染色体を必要とせず、すべての細胞周期において機能する。その一方、修復の正確性は低く、DNA末端の接合部において変異が起こりやすい。相同組み換え修復も二本鎖切断されたDNA修復メカニズムの一つであるが、姉妹染色体を利用するため非相同末端結合修復よりも正確な修復機構である。

非相同末端結合修復=姉妹染色体を利用しない。ミスが多い。
相同組換え修復=姉妹染色体を利用する。正確性が高い。
(3) 糖原性アミノ酸とケト原性アミノ酸
糖原性アミノ酸はアミノ酸の代謝の過程の代謝物としてオキサロ酢酸またはピルビン酸を生じるアミノ酸のことをいう。多くのアミノ酸が糖原性アミノ酸である。一方、ケト原性アミノ酸は代謝物としてアセト酢酸またはアセチルCoAを生じるアミノ酸のことをいう。ロイシンとリシンがこれに該当する。チロシン、イソロイシン、トリプトファン、フェニルアラニンの4種類は糖原性アミノ酸とケト原性アミノ酸の両方に該当する。

糖原性アミノ酸=代謝物として「オキサロ酢酸」or「ピルビン酸」を生じるアミノ酸
ケト原性アミノ酸=代謝物として「アセト酢酸」or「アセチルCoA」を生じるアミノ酸
覚え方はAZARASHIさんのブログを参考にしましょう!
問題を解き終えた感想
【2021年度の特徴】
- 比較的優しい問題が多い
- 「発生学」寄りの問題が出題された
- 全体として「分子生物学」よりも「生化学」の問題が多い印象
- DNA配列の設計に関する問題が出題された
2021年度の特徴は、問2の「プラスミドの調整に関する問題」が出題されたこと。
計算問題が出題されると、焦ってしまいますが、制限酵素はDNA配列を認識して切断する(切断部位はいつも同じ)ということさえ記憶していれば簡単に解けるので、ラッキー問題でした。
2019年度に出題された「ミカエリス・メンテン式」も落ち着いて考えられれば簡単に解ける問題なので、計算問題が出題されたらラッキーと覚えておきましょう(*^^*)
2021年度は全体的に簡単な印象です。
出題傾向として、より広く浅い問題が増えているように感じます。
2021年度の派生問題
好気呼吸においては、グルコースは(①)、(②)、(③)という3つの反応経路によって完全に分解され、水と二酸化炭素そして(④)分子のATPができる。
① 解糖系
② クエン酸回路
③ 電子伝達系
④ 38

「アルコール発酵」、「乳酸発酵」の問題とセットで、好気呼吸をおさえておこう!
[解糖系]
グルコース→2ピルビン酸+4[H]+2ATP
C6H12O6 + 2NAD+ + 2ADP + 2H3PO4 → 2CH3COCOOH + 2NADH + 2H+ + 2ATP + 2H2O
[クエン酸回路]
2ピルビン酸→20[H]+2ATP
2C3H4O3 + 6H2O + 8NAD+ + 2FAD + 2ADP + 2H3PO4 → 6CO2 + 8NADH + 8H+ 2FADH2 +2ATP + 2H2O
[電子伝達系]
24[H]→34ATP
24[H] + 6O2 → 12H2O + 34ATP
ということで、好気呼吸ではグルコース1分子で『合計38分子』のATPが作られます。
(①)、(②)、(③)は3大神経伝達物質と呼ばれ、脳内で神経現象のコントロールをしている。(①)は快楽や達成感、(②)は幸せ感、(③)やる気に関与している。
① ドーパミン
② セロトニン
③ ノルアドレナリン
タンパク質 A とタンパク質 B との相互作用を検証したい。蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)の実験技術を用いて検証する手順について6行以内で説明せよ。
まず組み換えDNA技術でタンパク質Aを指令するDNAの塩基配列を青色蛍光タンパク質を指令するDNAの塩基配列と結合させる。一方、タンパク質Bを指令するDNAの塩基配列を緑色蛍光タンパク質を指令するDNAの塩基配列と結合させる。最後に、これらの融合タンパクを細胞内で発現させ、紫色光を照射する。青色蛍光タンパクは紫色光で励起され青色光を発し、緑色蛍光タンパクは青色光で励起され緑色光を発するので、タンパクAとタンパクBが結合する場合、紫色光の照射により緑色光が検出される。
過去問リンク
- 2023年度の過去問(生物化学)
- 2022年度の過去問(生物化学)
- 2021年度の過去問(生物化学)
- 2020年度の過去問(生物化学)
- 2019年度の過去問(生物化学)
- 2018年度の過去問(生物化学)
- 2017年度の過去問(生物化学)
- 2016年度の過去問(生物化学)
- 2015年度の過去問(生物化学)
- 2014年度の過去問(生物化学)
- 2013年度の過去問(生物化学)
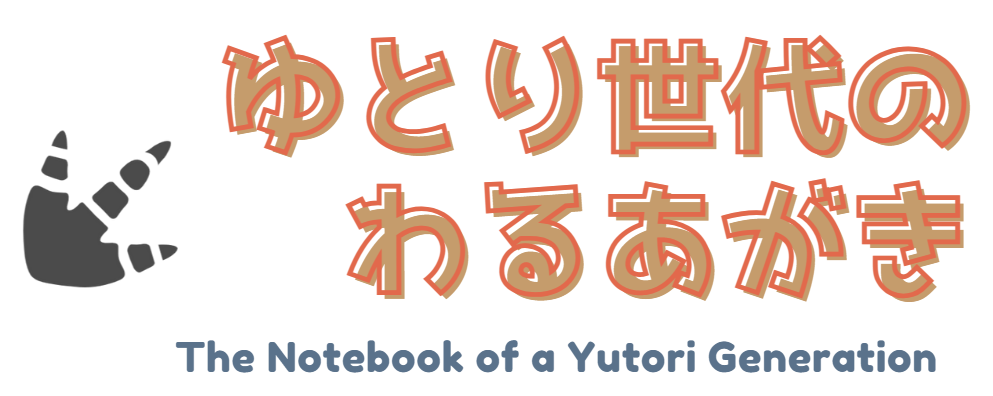
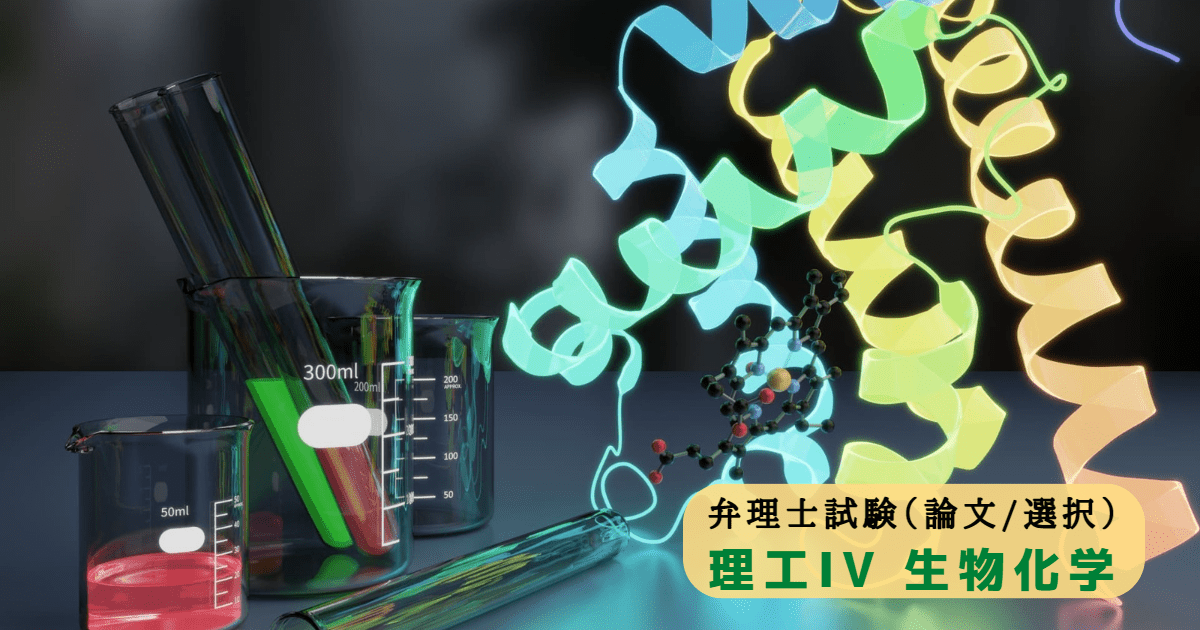




Comment