二次試験(論文/選択科目)の対策!
特許庁のWebサイトで公開されている過去問の中から、理工IV(生物)の「生物化学」を解いてみました。
今回は、2019年度(令和元年)の問題です。
ボクなりの回答と、ボクが考えた派生問題を共有させていただきます。

おかしな箇所があれば、Comment欄にてご指摘ください。
2019年度の過去問
問1(計40点)
1 以下の事項について、空欄の( ① )から( ⑳ )に適切な語若しくは数字を入
れよ。ただし、同じ番号には同じ語若しくは数字が入る。
(1) アミノ酸における共通の化学構造は( ① )基と( ② )基を併せ持つことである。( ① )基と( ② )基を結合している炭素原子のことを α 炭素原子と呼び、α炭素原子が不斉炭素原子であるとき、アミノ酸は実像と鏡像の関係にある( ③ )を取り得る。( ③ )体の一方は D 型、他方は L 型と呼ばれるがタンパク質を構成するのは( ④ )型だけである。また D 型と L 型の差を生じないアミノ酸として( ⑤ )が存在する。また( ⑥ )と( ⑦ )は不斉炭素原子を二つ持つアミノ酸である。
① アミノ
② カルボキシル
③ 光学異性体
④ L型
⑤ グリシン
⑥ トレオニン
⑦ イソロイシン

やっぱり、アミノ酸を覚えなおさないとか~…
ボクは、AZARASHIさんの語呂合わせで暗記することにしました┏○ペコッ
不斉炭素原子(4本の手がすべて異なる原子と結合する炭素原子)を二つもつアミノ酸は、「ITふせい」とします。
(I)イソロイシン
(T)トレオニン
(2) DNA の複製は DNA ポリメラーゼのみでは開始できない。DNA 複製は開始点で( ⑧ )が二重らせんをほどくことから開始する。複製は両方向に進行し、連続的に複製が進行する( ⑨ )鎖と不連続に進行する( ⑩ )鎖が存在する。( ⑨ )鎖では DNA複製のために 1 個の( ⑪ )を合成すれば良いが、( ⑩ )鎖では( ⑫ )フラグメントごとに( ⑪ )が必要となる。作られた( ⑫ )フラグメント同士は( ⑬ )によって連結され、新しい DNA 鎖が複製される。
⑧ DNAヘリカーゼ
⑨ リーディング鎖
⑩ ラギング鎖
⑪ プライマーRNA
⑫ 岡崎
⑬ DNAリガーゼ

学生の頃はあまり気にしてなかったけど、教科書によって登場する分子の名称が微妙に違う…
和訳の問題???
(3) ミカエリス・メンテン式は、酵素の反応速度と基質濃度との関係を示す式である。最大反応速度 Vmax の( ⑭ )の反応速度を示す基質濃度が Km であり Km が( ⑮ )ほど酵素と基質の親和性は大きい。ミカエリス・メンテン式に従う酵素は、反応速度がVmax の 20%である時の基質濃度を( ⑯ )倍すれば、反応速度は Vmax の 80%になる。
⑭ 半分
⑮ 小さい
⑯ 16

やっぱりミカエリス・メンテン式でたー!!!
80➗20🟰「よ、4倍!」(*⁰▿⁰*)
と答えたくなってしまうところですが、、、落ち着いて、ミカエリス・メンテン式(v=Vmax[S]/Km+[S])にあてはめてみましょう。
まず反応速度が「Vmaxの20%(v=0.2Vmax)」をあてはめると…
0.2Vmax=Vmax[S]/Km+[S]
[S]=0.25Km
次に反応速度「Vmaxの80%(v=0.8Vmax)」をミカエリス・メンテン式にあてはめると…
0.8Vmax=Vmax[S]/Km+[S]
[S]=4Km
よって、反応速度がVmaxの20%である時の基質濃度(0.25Km)を16倍すると反応速度がVmaxの80%の基質濃度(4Km)になります。
モヤモヤしてしまう場合は、それぞれの文字「Vmax」、「Km」、「[S]」をa、b、cといった具合に別の文字置き換えてみてみましょう。
(4) クエン酸回路(TCA サイクル)はアセチル CoA のアセチル基を 2 分子の( ⑰ )に酸化し、遊離するエネルギーを( ⑱ )産生に利用する仕組みである。クエン酸回路に関与する酵素群は( ⑲ )に存在し、アセチル CoA は( ⑳ )と縮合してクエン酸となり回路に組み込まれる。
⑰ CO2
⑱ ATP
⑲ ミトコンドリア
⑳ オキサロ酢酸
クエン酸回路を介して、グルコースがATPに変換されるまでの流れについては、2021年度過去問の派生問題をが参照ください。
クエン酸回路については、べんぜんさんの語呂合わせが大変わかりやすかったのでオススメさせて頂きます┏○ペコッ
問2(計20点)
2 生物化学に関する以下の問いに答えよ。
(1) 大腸菌のラクトースオペロンにおける転写制御について、以下の語を全て用いて4~6行程度で説明せよ。同一の語を複数回用いても良い。用いた語には下線を引くこと。
[プロモーター、リプレッサー、オペレーター、RNA ポリメラーゼ、転写]
Lacオペロンの転写開始は、転写活性化因子CAPとLacリプレッサーにより制御される。グルコースがないと、CAPがプロモーターのすぐ上流にあるアクチベーター結合部位に結合し、RNAポリメラーゼをプロモーターに引き寄せることでオペロンの転写を促進する。一方、ラクトースがないと、LacリプレッサーがLacオペレーターに結合して、オペロンの転写を抑制する。このようにしてLacオペロンはグルコースがなくラクトースがあるという2つの条件が満たされたときにだけ、高レベルで発現する。

これは頑張って覚えるしかない‼︎
余談ですが、「Lacオペロン」に限らず、1つのプロモータの活性は2種類の転写調節因子で制御されていることが多いらしいです。
(2) レトロウイルスの生活環について、以下の語を全て用いて4~6行程度で説明せよ。
同一の語を複数回用いても良い。用いた語には下線を引くこと。
[DNA、RNA、逆転写酵素、プロウイルス、宿主細胞、発芽]
まず、ウイルスのエンベロープが宿主細胞となる細胞の細胞膜の受容体と結合し細胞内にRNAと逆転写酵素を侵入させる。その後、逆転写酵素が作用し、プラス鎖ウイルスRNAを鋳型にマイナス鎖DNAを合成する。次いで、合成されたマイナス鎖DNAを鋳型にプラス鎖DNAを合成し、一本鎖RNAを二本鎖DNAに変換する。そして、二本鎖DNAは宿主細胞のDNAに組み込まれプロウイルスと呼ばれる状態になる。プロウイルスはウイルスRNAやメッセンジャーRNAを次々と合成し、完成したウイルスは宿主細胞から発芽する。

レトロウイルスは、逆転写酵素をもつRNAウイルスの総称。
レトロウイルスウイルスの代表例は、エイズをおこすエイズウイルス(HIV-1)、白血病をおこすヒトT細胞白血病ウイルスなど。
ちなみに、B型肝炎ウイルス(HVB)など、DNAウイルスにも逆転写酵素をもつものがいるそうです。
問3(計40点)
3 次の対比する二つの語に関して違いが分かるように6行程度で説明せよ。
(1) アポトーシスとネクローシス
アポトーシスは多細胞生物の細胞で増殖制御機構として管理・調節された能動的な細胞死である。ほとんどの場合、内容物がすべて細胞膜によって閉じ込められたままマクロファージ等によって貪食されるため、周囲の細胞に何の害も及ぼさない。一方、ネクローシスは栄養不足、毒物、外傷などの外的環境要因によっておこる受動的細胞死である。細胞の壊死を起こし通常は膨張・破裂して細胞内の様々な有機物質がばらまかれてしまうため、周囲に害を与える恐れのある炎症反応を引き起こす。

アポトーシス=能動的な細胞死
ネクローシス=受動的な細胞死
(2) 自然免疫と獲得免疫
自然免疫は体内に侵入してきた病原体や異常になった自己の細胞をいち早く感知し、それを排除する仕組みのことである。一つの分子が多種の異物や病原体に反応することができるが、特定の病原体に繰り返し感染しても自然免疫が増強することはない。一方、獲得免疫は感染した病原体を特異的に見分け、それを記憶することで同じ病原体に出会ったときに効果的に病原体を排除する仕組みのことである。自然免疫に比べると応答までにかかる時間が長い反面、病原体に対して強い殺傷能力を示す。

自然免疫=幅広い異物に素早く反応
獲得免疫=抗原特異的に強力な反応
(3) 体細胞分裂と減数分裂
1個の細胞が2個の細胞にわかれることを細胞分裂といい、「体細胞分裂」は体をつくっている細胞(体細胞)をつくるための細胞分裂のことをいう。体細胞分裂では、分裂の前と後で染色体の数は変わらない。一方、「減数分裂」は卵や精子などの生殖のための特別な細胞(生殖細胞)をつくるための特別な細胞分裂のことをいう。減数分裂によってできた生殖細胞は染色体の数が元の細胞の半分になる。

体細胞分裂=体細胞を作るための分裂
減数分裂=生殖細胞を作るための分裂
(4) 受動輸送と能動輸送
受動輸送とは、浸透現象などによってエネルギーを使用せずに物質を輸送する仕組みのことをいう。一方、能動輸送とはエネルギーを用いて低濃度側から高濃度側へ物質を輸送する仕組みのことをいう。浸透圧に逆らって物質を輸送するため、能動輸送ではエネルギーを使用するが、受動輸送は浸透現象などによる輸送であるため、エネルギーを使用しない。

受動輸送=エネルギーを使用しない
能動輸送=エネルギーを使用する
問題を解き終えた感想
【2019年度の特徴】
・2017年度の出題傾向と似ていて「分子生物学」が中心
・計算問題が出題された
・比較的簡単な問題が多い
2019年度の特徴といえばミカエリス・メンテン式の計算問題
式さえ暗記していれば中学レベルの数学で解けてしまうので、実はラッキー問題です。
他の問題にも当てはまりますが、難しい問題を解けるようになる必要はなく、浅く広く対策しておくことが重要だと感じました。
2019年度の派生問題
不斉炭素原子をもたないアミノ酸は(①)、酸性側鎖をもつアミノ酸は(②)と(③)、塩基性側鎖をもつアミノ酸は(④)、(⑤)、(⑥)である。
① グリシン(G)
② アスパラギン酸(D)
③ グルタミン酸(E)
④ リシン(K)
⑤ アルギニン(R)
⑥ ヒスチジン(H)

大学のテストで出たやつ‼︎
酸性側鎖をもつアミノ酸(2)
・アスパラギン酸
・グルタミン酸
塩基性側鎖をもつアミノ酸(3)
・リシン
・アルギニン
・ヒスチジン
ミカエリス・メンテン式はv=Vmax[S]/Km+[S]である。基質濃度をKm濃度の4倍で用いた時、その反応速度は最大反応速度(Vmax)の何%になるか。
80%
S=4Kmをミカエリス・メンテン式にあてはめると
v=4VmaxKm/Km+4Km
v=0.8Vmax
よって、基質濃度をKm濃度の4倍で用いた時、その反応速度は最大反応速度の80%になります。
ミカエリス・メンテン式で表される曲線のままVmaxとKmを正確に求めることが困難であるため、変換法が用いられる。最もよく用いられる変換法は(①)プロットである。その計算式はミカエリス・メンテン式(v=Vmax[S]/Km+[S])の逆数を取って整理し(②)となる。逆数を取るため、二重逆数プロットとも呼ばれることがある。
① ラインウィーバー・バーク
② 1/v=(Km/Vmax) x 1/[S] + 1/Vmax

これも大学で出たやつだ〜‼︎
ミカエリス・メンテン式とセットで問われるイメージです。
名称と式だけ覚えておきましょう。
過去問リンク
- 2023年度の過去問(生物化学)
- 2022年度の過去問(生物化学)
- 2021年度の過去問(生物化学)
- 2020年度の過去問(生物化学)
- 2019年度の過去問(生物化学)
- 2018年度の過去問(生物化学)
- 2017年度の過去問(生物化学)
- 2016年度の過去問(生物化学)
- 2015年度の過去問(生物化学)
- 2014年度の過去問(生物化学)
- 2013年度の過去問(生物化学)
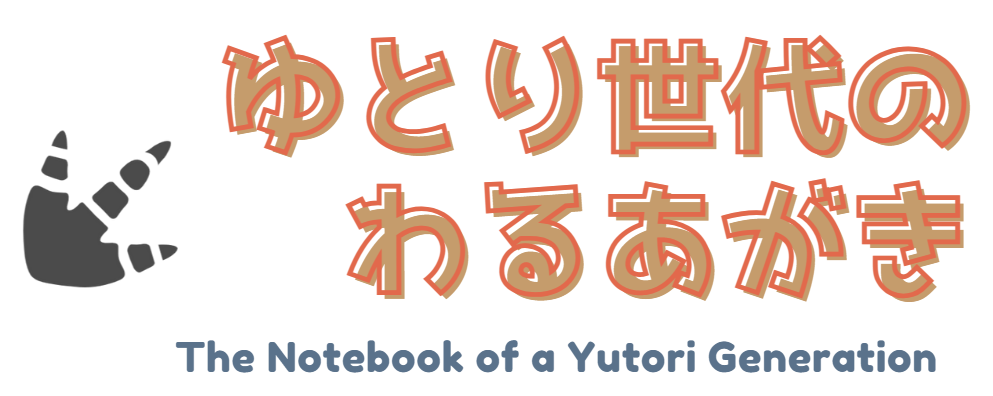
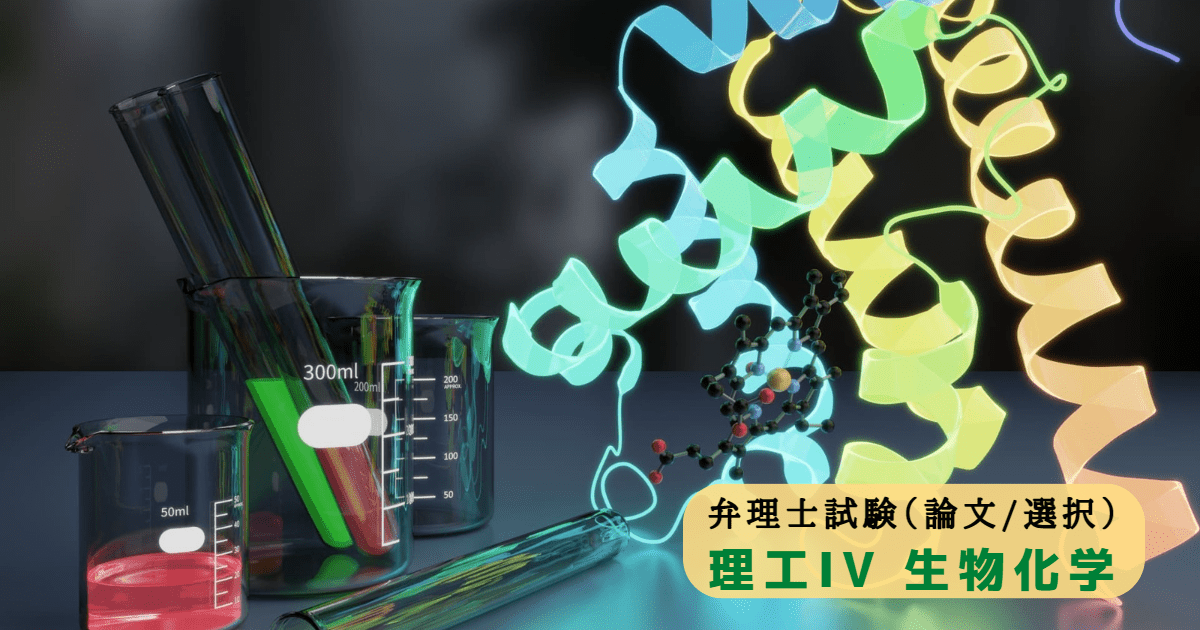




Comment