本日のテーマは「判例」
短答試験の対策として、知っておいた方が良さそうな判例とその要点をざっくりまとめました。
それでは早速いってみましょう!
特許/実用新案の判例
職務発明
◆ 日立製作所事件
(最高裁: 2006年)
→ 外国の特許を受ける権利を使用者に譲渡した場合でも、従業員は相当の利益を受ける権利を有する。
◆ 青色LED事件
(地方裁: 2004年)
→ 職務発明の相当な利益として約200億円の支払いが命令された。
産業上の利用可能性
◆ 外科手術の光学的表示方法事件
(東京高裁: 2002年)
→ 特許が認められる医薬品や医療機器と特許の認められない医療行為の相違点が示された。
新規性/進歩性
◆ 一眼レフカメラ事件
(最高裁: 1980年)
→ 29条1項3号の「頒布された刊行物」は、相当程度の部数が複製されて広く公衆に提供されているようなものに限られない。
◆ 第ニ箱尺事件
(最高裁: 1986年)
→ 29条1項3号の「頒布された刊行物」にマイクロフィルムが含まれることが示された。
◆ リパーゼ事件
(最高裁: 1991年)
→ 特許出願に係る発明の要旨認定は、特段事情がない限り特許請求の範囲に基づいておこなうべき。
補正/分割
◆ アースベルト事件
(最高裁: 1988年)
→ 補正前から実施発明が特許権の範囲内であった場合は、補正後に再度警告を要せず補償金請求権を行使できる
◆ 半サイズ映画フィルム録音装置事件
(最高裁: 1980年)
→ 分割して新たな出願とすることができる発明は、もとの出願の特許請求の範囲に限られず、明細書や図面に記載されているものを含む。
延長登録出願
◆ 新規ポリペプチド事件
(最高裁: 1997年)
→ 医薬品における67条4項の「特許発明が実施できなかった期間」の最終日は「製造販売の承認が申請者に到達した日の前日」であることが示された。
権利の効力
◆ 生理活性物質測定方法事件
(最高裁: 1999年)
→ 方法の発明に関する特許権に、物を生産する方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることはできない。
◆ グアニジノ安息香酸誘導体事件
(最高裁: 1999年)
→ 後発医薬品の承認申請を目的に、特許発明の医薬品を生産し、これを使用して必要な試験を行うことは、特許権侵害とはならない。
◆ プラバスタチン事件
(最高裁: 2015年)
→ 物の発明に製造方法が記載されている場合でも、当該物と構造、特性が同一であれば、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定される(PBPクレーム)
→ PBPクレームは出願時において当該物を構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的ではないという事情が存在するときに限られる
◆ ボールスプライン軸受事件
(最高裁: 1998年)
→ 特許発明と異なる部分を有する場合でも、以下の条件を全て満たせば均等論侵害が成立する
1. 異なる部分が特許発明の本質部分でない
2. 異なる部分を置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する
3. 製造時点で当業者が容易に想到できた
4. 出願時点で当業者が容易に推考できない
5. 対象製品が意識的に除外した物でない
◆ マキサカルシトール事件
(最高裁: 2017年)
→ 出願時点で出願人が容易に想到できた場合でも、均等論侵害が成立
→ 明細書等に対象製品を記載していた場合、特許請求の範囲から意識的に除外したものみなす
権利の行使
◆ BBS事件
(最高裁: 1997年)
→ 特許権者又は通常実施権者が譲渡した特許製品の特許権は消尽する。
→ 販売先から日本を除外する旨を合意し、特許製品にその旨を明確に表示した場合を除き、新正商品の並行輸入は特許権を侵害しない。
◆ インクタンク事件
(最高裁: 2007年)
→ 譲渡により特許権が消尽したものであっても、同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められたときは、その特許製品に特許権を行使できる。
◆ リガンド分子事件
(最高裁: 2005年)
→ 特許権に専用実施権を設定した場合でも、特許権者は当該特許権に基づく差止請求権を行使できる
先使用権
◆ ウォーキングビーム炉事件
(最高裁: 1986年)
→ 即時実施の意図を有し、客観的に認識される態様、程度において表明されていれば、事業の準備として認められる。
→ 先使用権の効力は、特許出願の際に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ。
訴訟
◆ メリヤス編み機事件
(最高裁: 1976年)
→ 審判で争われていない無効理由を審判取消訴訟で争うことはできない。
◆ 食品包装容器事件
(最高裁: 1980年)
→ 実用新案に関する無効審決の取消訴訟において、審判で提出していない資料を新たに提出して、出願当時の技術常識を認定することが認められた。
◆ パチンコ装置事件
(最高裁: 2001年)
→ 特許が共有にかかるときでも、単独で取消決定に対する取消訴訟を提起できる。
◆ 磁気治療器事件
(最高裁: 1995年)
→ 特許を受ける権利が共有の場合は、拒絶審決に対する審決取消訴訟は、共有者全員で提起する必要がある
意匠法の判例
意匠の定義
◆ コネクター接続端子事件
(東京高裁: 2005年)
→物品の取引に際し、拡大して観察することが通常である場合には、肉眼で認識できないとしても視覚を通じて美観を起こさせるものにあたる
◆ 減速機付きモーター事件
(東京高裁: 2003年)
→流通過程において外観に現れず視覚を通じて認識することができない物品の隠れた形状は考慮することができない
進歩性
◆ 可撓性ホース事件
(最高裁: 1970年)
→ 同一類似の公知意匠を引用して、3条2項が適用されることもあり得る。
利用抵触
◆ 学習机事件
(地方裁: 1971年)
→ 利用関係を深く理解する上で目を通しておくべき判例。
商標法の判例
3条/4条
◆ ジョージア事件
(最高裁: 1985年)
→ 3条1項3号「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の判断において、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要求されるわけではない
◆ EARL GREYS事件
(東高裁: 1977年)
→商標がその商品の品質を表示するものとして取引業者間で認識されているものでも 「指定商品の品質を表示するもの」に該当する。
◆ ダリ事件
(東京高裁: 2001年)
→ 著名な歴史上の人物の略称に類似するため、4条1項7号に該当すると判断された。
◆ カムホート事件
(最高裁: 2003年)
→ 4条1項8号に該当する商標の登録を受けるためには、査定時において8号括弧書の承諾を要する。
◆ レールデュタン事件
(最高裁: 1998年 )
→ 4条1項15号の混同にいわゆる広義の混同(密接な営業上の関係又はグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信させるおそれ)が含まれる。
補正/分割
◆ eAccess事件
(最高裁: 2004年 )
→ 訴訟継続中の分割と同時の補正は68条の40に該当せず遡及効がないため、訴訟継続中は拒絶理由がない指定商品指定役務について新たな商標登録出願とする必要がある。
権利の効力
◆ テレビ漫画事件
(地方裁: 1980年)
→ カルタに付した「テレビまんが」の標章は、商標的使用ではない(登場人物が漫画映画由来であることを表示するにすぎない)と判断され、登録商標「テレビマンガ」の権利侵害が否定された。
◆ 巨峰事件
(地方裁: 1971年)
→ ダンボールに付した「巨峰」「KYOHO」の標章は、商標的使用ではない(内容物である巨峰ぶどうの表示)と判断され、包装用容器の登録商品「巨峰」の権利侵害が否定された。
◆ POS事件
(地方裁: 1988年)
→ 書籍の題号の一部として付した「POS」の標章は、商標的使用ではない(書籍の内容を示しているにすぎない)と判断され、印刷物の登録商品「POS」の権利侵害が否定された。
◆ 氷山印事件
(最高裁: 1968年)
→ 商標の外観、観念又は呼称は出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、その一において類似するものでも、商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについてはこれを類似商標と解すべきでなはない。
◆ つつみのおひなっこや事件
(最高裁: 2008年)
→ 商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは特別な場合を除き許されないというべき。
権利の行使
◆ ポパイ・マフラー事件
(最高裁: 1985年)
→ 登録商標「ポパイ」は著名性を無償で利用しているものに他ならず、著作権者の了承を得て人気漫画「ポパイ」の標章を付した商品の販売しているものに対する商標権の侵害を主張することは、権利の濫用にあたると判断された
◆ フレッドペリー事件
(最高裁: 2003年)
→ 登録商標と同一の商標を付されたものを輸入する行為は、以下を全て満たす場合、商標権侵害としての実質的違法性を欠く。
・適法に付された商標である
・外国と日本の商標権者が経済的に
同一人と同視し得るような関係がある
・日本の商標権者が品質管理できる立場にある
◆ マグアンプ事件
(地方裁: 1994年)
→ 商品の品質に変化をきたすおそれがあるか否かを問わず商標権者の承諾を得ずに小分けし再度流通に置くことは、商標権の侵害を構成するものといわなければならない。
◆ 小僧寿し事件
(最高裁: 1997年)
→ 損害の発生していないことが明らかな場合は、使用料相当額を請求できないことが示された。
不使用取消し審判
◆ シェトワ事件
(最高裁:1991年)
→ 登録商標使用の事実は不使用取消審判の審決に対する審決取消訴訟の事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される
不競法の判例
商品等表示の定義
◆ 日本ウーマン・パワー事件
(最高裁: 1983年)
→ 商品等表示の類似性には、外観、呼称、観念だけでなく、取引の実情も考慮すべき。
◆ ウェットスーツ事件
(地方裁: 1981年)
→ 色彩の組み合わせであっても周知性を獲得したものは商品等表示として保護される
◆ 究極の選択事件
(地方裁: 1989年)
→ 商品等表示であるためには、出所表示機能又は自他商品識別機能を有することが必要であることが示された。
◆ トロピカルライン事件
(地方裁: 1995年)
→ 色彩の組み合わせについて、自他識別機能又は出所表示機能を有するに至った場合は、他人の商品表示等となり得る
◆ かに看板事件
(地方裁: 1981年)
→ 商品等表示として動く表示が含まれることが示された。
◆ スピードラーニング事件
(知財高裁: 2015年)
→ 需要者に対する訴求力が高い場合や、広告や宣伝で広く浸透した場合には、キャッチフレーズであっても自他識別機能又は出所表示機能を有する場合がある
◆ ホーキンス事件
(地方裁: 1995年)
→ 商品の包装は本来商品の出所表示を目的とするものではないが、第二次的に標品表示性を取得することもあり得る。
◆ フットボール・シンボルマーク事件
(最高裁: 1981年)
→ 他人には、商品等表示の持つ出社識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているグループも含まれる。
◆ 少林寺拳法事件
(地方裁: 1973年)
→ 非営利法人の名称であっても商品等表示として保護されることが示された。
◆ 天理教事件
(最高裁: 2005年)
→ 取引会社における事業活動と評価できない活動、例えば、宗教法人の本来的な宗教活動及びこれと密接不可分の関係にある事業は、「営業」に該当しない。
混同惹起行為
◆ 勝烈庵事件
(地方裁: 1981年)
→ 一地方での周知性が認められた事例
◆ アメックス事件
(最高裁: 1993年)
→ 第三者の使用によって周知性を獲得した場合にも、周知性は認められる。
◆ アーク・エンジェルズ事件
(地方裁: 2007年)
→ 周知性の判断に際して、新聞や雑誌における当該名称の使用状況及び頻度が考慮された事例
◆ スナックシャネル事件
(最高裁:1995年)
→ 1条1項1号の著名標示冒用行為が創設されたあとであっても、1条1項1号の周知標示に広義の混同が含まれることが示された。
著名標示冒用行為
◆ ラブホテルシャネル事件
(地方裁: 1984年)
→ 著名標示保護の観点からなされた判決。混同を認定した点について疑問視され、著名表示冒用行為が創設されるきっかけとなった。
◆ ベレッタ事件
(地方裁: 1998年)
→ 実銃の標章をモデルガンに付して販売しても、出所表示機能・自他商品識別機能を有する態様での使用にあたらないの判断された。
形態模倣行為
◆ エルメス・バーキン事件
(地方裁: 2000年)
→ 原告製品の形態は、著名なエルメス社のバーキンの形態を模倣したものであるため、損害賠償請求は認められない。
◆ ギブソン・ギター事件
(地方裁: 1998年)
→ ギターの形態が商品等表示として認められた事例
◆ ルイ・ヴィトン事件
(知財高裁: 2018年)
→ 模様のみで、商品等表示として認められた事例
誤認惹起行為
◆ 原石ベルギーダイヤ事件
(東京高裁: 1978年)
→ ダイヤモンドのように加工のいかんによって商品価値が大きく左右されるものについては、その加工地が一般に「原産地」であると判断された。
著作権法の判例
著作物の定義
◆ カタログ写真事件
(東京高裁: 2005年)
→ 撮影にあたってどのような技法が用いられたかに関わらず、結果として得られた写真に独自性が表れていれば写真の著作物としての創作性を認めるべき
◆ 雪月花事件
(東京高裁: 1999年)
→ 書は、文字の形の独創性、線の美しさと微妙さ、文字群と余白の構成美、運筆の緩急と抑揚、墨色の冴えと変化、筆の勢い、ひいては作者の精神性までをも見る者に感得させる造形芸術
◆ スローガン事件
(東京高裁: 2001年)
→ 交通スローガンにおける著作性の有無及び類似性の範囲に関する見解が示された
◆ 京都大学博士論文事件
(知財高裁: 2005年)
→ 盗用した実験データもとに研究論文を執筆した場合であっても、著作者であることが示された。
◆ SMAPインタビュー事件
(東京地裁: 1995年)
→ インタビューで得た情報をもとに文章を作成した場合、文書表現の作成に口述者が創作的に関与したといえなければ、口述者は文章の著作者とはならない
同一性保持権
◆ ときめきメモリアル事件
(最高裁: 1999年)
→ ゲームソフトが映画の著作に該当すること、また改変したメモリーカードの輸入及び販売行為が同一性保持権を侵害すると判示された。
氏名表示権
◆ ジョン万次郎事件
(知財高裁:2005年)
→ 氏名表示権は他人名義で表示することを許容する規定が設けられていないため、真の創作者以外の者を創作者として表示することの合意があったとしても、無効であることが示された。
演奏権
◆ クラブキャッツアイ事件
(最高裁: 1988年)
→ カラオケスナックにおいて、著作権者の許諾なく客に歌唱させる行為は店経営者による演奏権侵害である。
複製権/頒布権
◆ ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件
(最高裁:1975年)
→ 著作物の複製とは既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう
◆ 中古ゲームソフト事件
(最高裁: 2001年)
→ ゲームソフトが映画の著作物になる場合もあるが、劇場用の映画の著作物とは異なり、その後の流通において、頒布権の効果は及ばない。
貸与権
◆ ビデオメイツ事件
(最高裁: 2001年)
→ カラオケ装置のリースにおいて、リース先のカラオケ店が著作権侵害を行った場合、リース業者が法的責任を負う
翻案権
◆ 江差追分事件
(最高裁: 1999年)
→ 本案とは、既存の著作物に依拠し、その表現上の本質的特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、変更等を加えて、新たに思想感情を創作的に表現して、これを接するものに既存の著作物の表現上の本質的特徴を直接感得させることができる著作物を創作する行為とされた。
二次的著作物の利用
◆ キャンディキャンディ事件
(最高裁: 2000年)
→ 二次的著作物の利用に際して、二次的著作物の作者は原作者の合意を得る必要がある。
権利の制限
◆ モンタージュ写真事件
(最高裁: 1976年)
→ 著作物の引用には、引用して利用する物と引用されて利用される物とを明確に区別して認識することができ、かつ両著作物との間に主従関係が認められなければならない
◆ バス車体絵画事件
(地方裁: 2001年)
→ 車体に絵を描いた路線バスについては、美術の著作物を「恒常的に設置した」というべきであることが示された。
権利の効力
◆ 顔真卿自書建中告身帖事件
(最高裁: 1984年)
→ 著作権の存続期間満了後、その著作物は公有財産(パブリック・ドメイン)となる。
名誉回復措置請求
◆ パロディ事件
(最高裁: 1983年)
→ 意に反する著作物の改変により名誉感情が害されただけでは、名誉回復の措置請求は認められない。
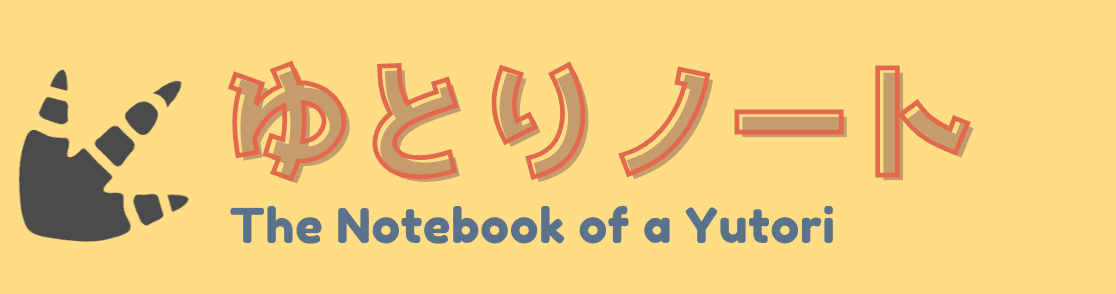


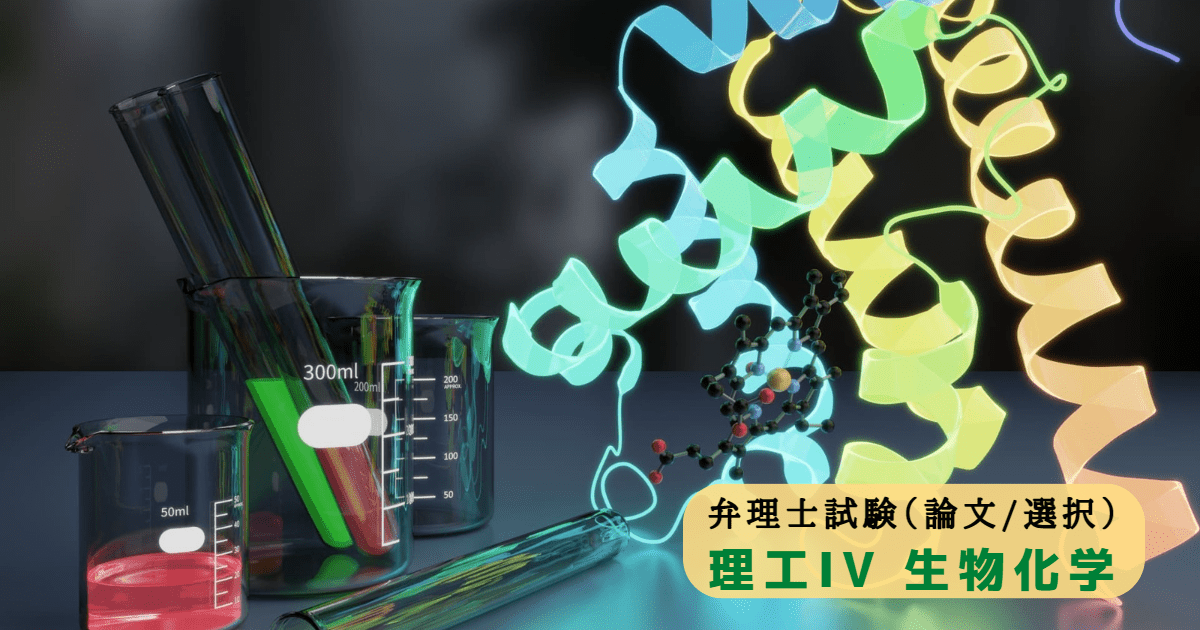
Comment